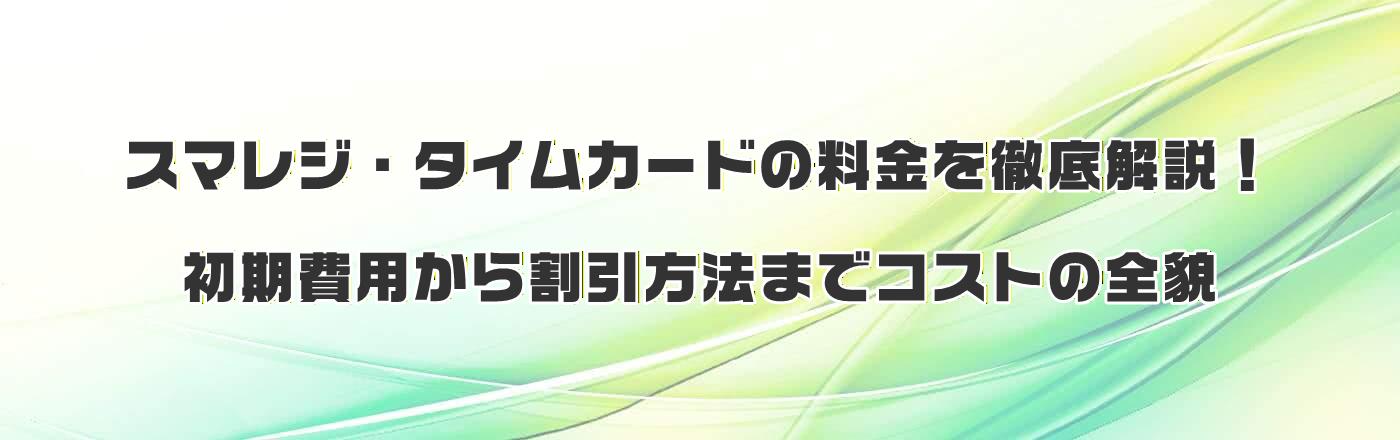
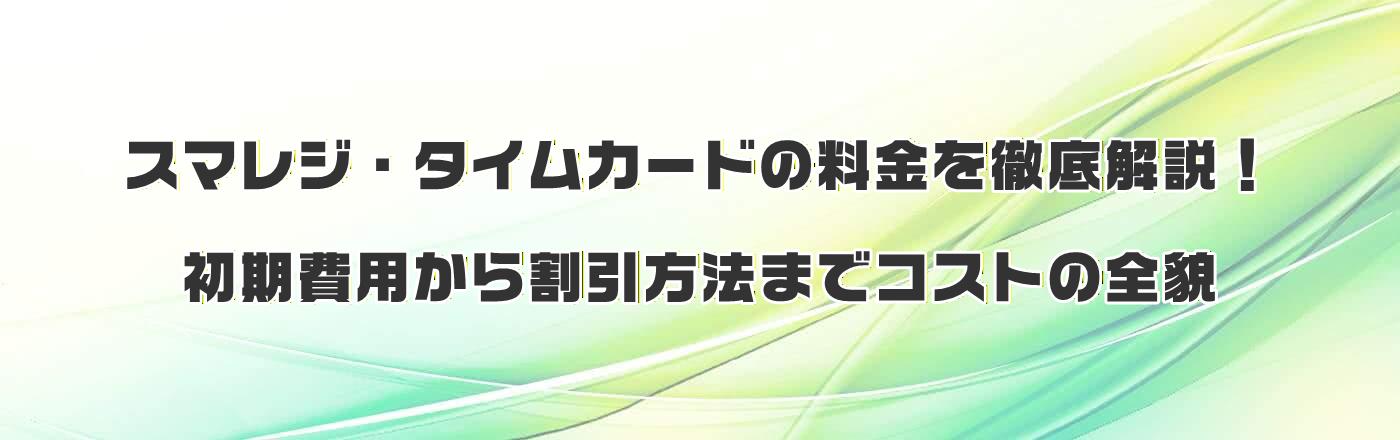
ーこのページにはPRリンクが含まれています。ー
この記事では、
「クラウド勤怠管理サービス「スマレジ・タイムカード」の料金はいくらなの?」
「料金以外でどのような費用が必要になるの?」
「追加で費用がかかる場合はあるの?」
といったことが知りたい方におすすめです。

スマレジ・タイムカードの料金は4プラン制です。基本料金(10名まで)は、スタンダードプランが月額0円、プレミアムが2,420円、プレミアムプラスが4,840円、エンタープライズが7,260円です。11名以上は1名ごとに追加料金(110円〜770円)が発生します。(価格は税込)
料金以外に必要な費用として、初期設定費用は0円です。ただし、打刻に専用アプリ(iOSのみ対応)を利用したい場合は、iPadなどのデバイス購入費用が別途かかります。既存PCやスマホのブラウザ打刻なら追加費用は不要です。
追加費用は、下位プランで日報管理やワークフロー(申請承認)、電話サポートなどの上位機能をオプションとして追加する場合に発生します。
クラウド勤怠管理システムの導入を検討する際、最も気になるのが「結局、総額でいくらかかるのか?」という点です。
「スマレジ・タイムカード」は高機能でありながら、コストパフォーマンスに優れていると評判ですが、その料金体系は少し複雑です。
この記事では、プロの視点からスマレジ・タイムカードの料金を徹底的に分解し、
「基本料金はいくら?」
「初期費用や追加オプションは?」
「どうすれば一番安く使えるの?」
といった疑問を持つあなたが、導入前に知っておくべき全てのコスト情報を解説します。
【結論から】スマレジ・タイムカードの料金体系早わかり表

まずは全体像を掴むために、4つの主要プランの料金と特徴を一覧表にまとめます。
料金はすべて税込表記です。
| プラン名 | 主な対象 | 基本月額料金(10名まで) | 追加料金(11名以上/1名ごと) | 主な機能 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 10名以下の小規模事業者 | 0円 (11名以上は1,210円/月) |
110円/人 | 基本勤怠管理(打刻など) | まずは無料で試したい場合に最適 |
| プレミアム | 成長中の中小企業 | 2,420円/月 | 385円/人 | シフト管理、休暇管理、給与計算連携 | 人気No.1のバランス型プラン |
| プレミアムプラス | データ活用したい小売・飲食業 | 4,840円/月 | 495円/人 | プレミアム機能に加え、労務アラート、人時売上高分析、マイナンバー管理 | スマレジPOS(有料)利用で基本料金が2,420円に割引 |
| エンタープライズ | 大規模・プロジェクト型組織 | 7,260円/月 | 770円/人 | 全機能に加え、日報・プロジェクト工数管理、ワークフロー(申請承認) | 電話サポート標準搭載 |
この表が示す通り、スマレジ・タイムカードの料金は単純な「1人いくら」ではなく、少し特殊な仕組みになっています。
次の章から、この詳細を深く掘り下げていきましょう。
1. 料金はいくらなの? 4つのプラン詳細
スマレジ・タイムカードの料金モデルは、「ハイブリッド型」と呼ばれます。
これは、一定人数(10名)までは固定の「月額基本料金」がかかり、それを超えた分は1名あたりに追加料金(PUPM: Per-User, Per-Month)が発生する仕組みです。
このモデルは、小規模なうちはコストを固定でき、事業が成長して人員が増えても柔軟に対応できるスケーラビリティ(拡張性)が魅力です。
各プランで使える機能と料金を見ていきましょう。
プラン1:スタンダード(10名まで月額0円)
従業員10名まで、なんと月額0円で利用できるプランです。
機能は出退勤の打刻など、勤怠管理の基本的なものに限定されます。
「まずは紙のタイムカードから脱却したい」というスタートアップや小規模事業者に最適です。
ただし、11名以上で利用する場合、月額1,210円の基本料金+11人目から1名ごとに追加料金110円が発生する点に注意が必要です。
無料で使えるのは、あくまで10名以下の事業者限定となります。
プラン2:プレミアム(人気No.1の成長企業向け)
基本料金:月額2,420円(10名まで)
追加料金:1名あたり385円(11名以上)
「人気No.1」とされている、機能とコストのバランスが最も取れたプランです。
スタンダードの基本機能に加え、シフト管理、休暇管理、給与計算ソフトとの連携(CSV出力)、年末調整機能までカバーします。
基本的な勤怠管理業務を大幅に効率化したい、成長中の中小企業に選ばれています。
プラン3:プレミアムプラス(POS連携で最強コスパ)
基本料金:月額4,840円(10名まで)
追加料金:1名あたり495円(11名以上)
プレミアムの機能に加え、より高度な労務管理と分析機能が搭載されています。
労働基準法違反の可能性を警告する「労務アラート」、マイナンバー管理、法定三帳簿(労働者名簿など)の出力、さらに「人時売上高分析」(従業員1人あたりの売上効率を分析する機能)が可能です。
このプランの最大の戦略的ポイントは、「スマレジPOS(有料プラン)」を利用していると、基本料金が半額の2,420円になることです。
つまり、プレミアムプランと全く同じ基本料金で、これらの高度な機能がすべて使えるようになります。
すでにスマレジPOSを導入している小売店や飲食店にとって、実質的に一択となるプランです。
プラン4:エンタープライズ(全機能搭載モデル)
基本料金:月額7,260円(10名まで)
追加料金:1名あたり770円(11名以上)
最上位プランであり、下位プランの全機能に加えて、組織運営を高度化するツールが満載です。
日報管理、プロジェクトごとの工数管理、そして休暇申請や経費精算を電子化する「ワークフロー(申請・承認)機能」が使えます。
また、このプランのみ標準で電話によるコールセンターサポートが含まれています。
複数のプロジェクトを抱える専門サービス業や、詳細な工数管理が必要な大企業向けのソリューションです。
2. 料金以外で必要な費用は?(初期費用・ハードウェア)

月額料金(ランニングコスト)以外に、導入時にかかる初期費用(イニシャルコスト)も気になるところです。
初期設定費用は0円
スマレジ・タイムカードは、アカウント作成やシステム導入の初期設定費用は0円です。
ソフトウェアの導入ハードルは非常に低いと言えます。
必須のハードウェアは? (PC・スマホ・iPad)
打刻を行うためのデバイス(端末)が必要です。
スマレジ・タイムカードは「BYOD(Bring Your Own Device)」モデルを採用しており、専用の打刻機を販売していません。
(BYODとは、従業員が個人で所有するデバイスや、会社がすでに持っているデバイスを業務利用することです。)
具体的には、既存のPCやスマートフォン、タブレットのWebブラウザから打刻が可能です。
そのため、すでにある機材を活用すれば、追加のハードウェア投資0円で運用を開始できます。
隠れたコスト? 専用アプリはiOSのみ
ここで一つ、見落としがちな注意点があります。
Webブラウザからの打刻はどのOS(Windows, Mac, Android, iOS)でも可能ですが、より直感的に操作できる専用のタイムカード打刻アプリは、iOS(iPad, iPhone)にしか対応していません。
もし、店舗のレジ横に打刻専用のタブレットを置きたい場合や、アプリの快適な操作性を求める場合、新たにiPadなどのApple製品を購入する費用が発生する可能性があります。
社内がAndroidデバイスで統一されている企業は、この点を考慮に入れる必要があります。
3. 追加で費用がかかる場合は?(オプション機能)
基本プラン料金以外にも、特定の機能を追加することで費用が発生する場合があります。
必要な機能だけ追加できる「アラカルト」オプション
エンタープライズプランに標準搭載されている高度な機能の一部は、下位プラン(プレミアム、プレミアムプラス)でも個別にオプションとして追加(アラカルト)できます。
- コールセンターサポート: +55円/人・月
- 日報管理: +110円/人・月
- ワークフロー: +275円/人・月
- プロジェクト管理: +330円/人・月
(※料金はすべて税込)
オプション追加の注意点:エンタープライズへの移行判断
このオプション料金は、戦略的に設定されています。
例えば、プレミアムプラスプラン(追加料金495円/人)の人が、「ワークフロー(275円)」と「プロジェクト管理(330円)」の両方を必要とした場合、オプション料金だけで月額605円/人が追加でかかります。
この追加額(605円)は、エンタープライズプランへのアップグレード差額(770円 - 495円 = 275円)を大幅に上回ります。
つまり、高度なオプションを2つ以上追加する場合は、それらを個別に追加するよりも、エンタープライズプランへアップグレードした方が安くなるように設計されています。
必要な機能が増えてきたら、プラン全体の移行を検討することが、結果的に総所有コスト(TCO: Total Cost of Ownership)の削減に繋がります。
4. 料金が更に安くなる4つの方法
スマレジ・タイムカードのコストを最適化し、さらに安く利用するための4つの戦略的な方法をご紹介します。
方法1:60日間の全機能無料トライアルを使い倒す
新規アカウントを作成すると、最上位のエンタープライズプランを含む全機能を、60日間も無料で試用できます。
これは業界でも最長クラスのトライアル期間です。
この期間を「単なる機能確認」で終わらせてはいけません。
「自社にとって本当に必要な機能は何か」を見極めるための「診断期間」として最大限活用しましょう。
特に、プロジェクト管理やワークフローなどの上位機能を実際に試し、業務改善に繋がるか評価します。
トライアル終了後、申し込みをしなければ自動で無料のスタンダードプランに移行するため、意図せず課金される心配もありません。
方法2:【最重要】スマレジPOS連携割引を活用する
前述の通り、これは最も強力なコスト削減策です。
スマレジPOSレジ(有料プラン)を利用している企業は、プレミアムプラスプランの基本料金(月額4,840円)が半額の2,420円になります。
これにより、プレミアムプラン(月額2,420円)と全く同じ基本料金で、労務アラートや人時売上高分析といった遥かに高度な機能が手に入ります。
小売業や飲食業で、POSレジと勤怠管理の両方の導入を検討している場合、スマレジのエコシステム(関連サービス群)にまとめて乗ることで、最大のコストメリットが享受できます。
方法3:IT導入補助金を活用する (条件あり)
スマレジは「IT導入補助金」の対象製品であり、スマレジ自体が申請をサポートする「IT導入支援事業者」に認定されています。
この制度を使えば、導入費用の大部分(最大3/4や4/5)が補助される可能性があります。
ただし、利用には厳しい条件があるため注意が必要です。
- 対象プランの制限: 補助金の対象は「プレミアムプラス」以上のプランのみです。
- 一括前払い義務: 申請時に「2年分のサービス利用料」を一括で前払いする必要があります。(補助金は後から交付されます)
- 導入期間: 申請から採択まで最低3ヶ月程度かかり、その間は導入できません。
- 事業実績: 新規開業直後の事業者は対象外など、事業実績の要件があります。
キャッシュフローに余裕があり、導入を急がない安定企業にとっては強力な選択肢となります。
方法4:紹介キャンペーンを利用する
既存のスマレジ利用者に紹介してもらうことで、紹介者と被紹介者の双方に20,000円分のAmazonギフト券が贈られるキャンペーンが実施されている場合があります。
(※プレミアムプラス以上の契約など、適用条件があります)
サービス料金の直接的な割引ではありませんが、導入時に必要なiPadなどのハードウェア費用を相殺できる、実質的な金銭的メリットとなります。
まとめ:自社に最適なプランを見極める方法

スマレジ・タイムカードの料金について、詳細に解説してきました。
最後に、あなたの会社に最適なプランを選択するための意思決定ステップをまとめます。
- まずは「60日間無料トライアル」を申し込む。
全ての判断はここから始まります。全機能を試し、「絶対に譲れない機能」と「あれば便利な機能」をリストアップしてください。 - 勤怠管理の対象となる「従業員数」を正確に把握する。
10名以下か、11名以上かで、まずスタンダードプラン(無料)が選択肢になるか決まります。 - 「スマレジPOS」を利用しているか(するか)確認する。
もしYESなら、「プレミアムプラスプラン(POS割引)」が機能・価格の両面で最有力候補です。 - 「総所有コスト(TCO)」で試算する。
月額料金だけでなく、専用アプリのためにiPadが必要なら、そのハードウェア代も含めて総コストを計算しましょう。 - 補助金やキャンペーンの条件を確認する。
IT導入補助金(2年縛り・一括払い)の条件が飲めるかなど、自社の状況と照らし合わせます。
これらのステップを踏むことで、機能に過不足がなく、最もコスト効率の高いプランを合理的に選択できるはずです。
ぜひ、自社の成長戦略に最適な勤怠管理システム導入を実現してください。
